2019年06月24日
超軽量なM4をフルメタルで自作する! その③
その②からの続きです。
さて、前回でシリンダー、チャンバー、バレルの中心線を合わせるという作業は完了しました。
今回はレシーバーの細かいレバー類を取り付け&アウターの長さを決定していきたいと思います。
まずはロアレシーバーの細かいパーツを組み上げていきます。

今回は軽量化&ドレスアップのため、G&Pのプラ製トリガーガードを取り付けていきます。

形状はナイツのやつですね。
G&Pのトリガーガードの穴の内径がプッシュピンとスプリングよりも狭かったので4mmドリルで拡張!!

海外パーツに海外パーツを取り付けるには兎にも角にも加工が必須ですね。
取付完了!

マガジンキャッチはこれを使います。
SP製のアルミ削り出しのやつですね。

アンビでボタンが大型化されています。非常に軽量で18gしかありません。

ボルトリリースレバーは東京マルイ純正のものを使用します。


ロワレシーバーはこんな感じです。
お次はアッパーレシーバーです。
ダミーボルトを取り付けていきます。

このレシーバーに付属していたダミーボルトが取り付けできないってどういうこと~!!!

つくづく微妙ですね~G&Gのマグネシウムレシーバー。
まぁ古い製品なのでしょうがないですね。
怒りを込めてレシーバー側の干渉する段差をリューターで削りました(笑)ダミーボルトの羽をカットするのでも良かったのですがね。

イジェクションポートも付属の物を取り付けましたがロックピンが無いので空きっぱなしという仕様!!う~ん。そのうちマルイのに変えよう。

レシーバーに付属していたボルトフォアードアシストノブが重く感じたので今回はレトロアームズのものを取り付けます。

これもメカボックスと同じようにA7075(超々ジュラルミン)からの削り出しです。
G.A.Wさんで取り扱いがなかったのでレトロアームズの公式通販ページから個人輸入しました。
グレーとブラックを1個づつ注文しましたがほぼ同じ色でした(汗)
左がグレー、右がブラック

肉眼だとよーく目を凝らしてみないと違いが分からないレベルです。
レシーバーに付属していたスチール製のフォアードアシストノブは22g

レトロアームズのノブは8g

微々たる差ですが手に持ってみると結構違いを感じるんですよね。
軽い銃を作るにはこういったパーツ一つ一つの重量が積もりに積もっていくので拘ります。
チャージングハンドルはG&Pのプラスチック製のものにします。軽量です。

めちゃくちゃ大げさなシボ加工がされているうえ、やたらテカテカなのが気になる(笑)
これでアッパーは完成!

アウターはこれを使います。

こんな感じにしました。アウターバレルよりKM企画のサイレンサーの方が軽いのでサイレンサーをアウターの代わりに使う感じですね。

いつものスタイルです(笑)

本当はSLRのハイダーにしてハンドガードとお揃いにしたかったのですが重量が90gもあり、ハイダーの中でも重い方なので今回はナシ。

レールを取り付けるとマズルはほぼツライチになります。

ちょっと寸詰まり感がありますがこんなもんかな~と。
フリップアップサイトとハンドストップでも付ければ印象良くなるんじゃないかなと。
本当はこんなスタイルが理想でした。

諸々組み付けてここまで形になりました。

アウターがこの長さだとインナーバレルは21cmになりますね。今回もこの21cmの長さを基準にメカボックスの中身を作っていくことにします。
セレクターはマガジンキャッチに付いてきたものをとりあえずで付けてみましたがミリタリー感の無い形状をしているのでマルイ純正にしようかな・・・。

トリガーもレトロアームズの面白い形のやつにしましたがまだアルマイト加工(色付け)していないので変更の余地ありですね。
あとはワイヤーストックの軽量化もする予定です。

このロッドがスチール製で重たいので軽量なアルミパイプに置換したいと考えておりますがそれはまた今度ですね。
ということでまた次回!
その④へ
さて、前回でシリンダー、チャンバー、バレルの中心線を合わせるという作業は完了しました。
今回はレシーバーの細かいレバー類を取り付け&アウターの長さを決定していきたいと思います。
まずはロアレシーバーの細かいパーツを組み上げていきます。

今回は軽量化&ドレスアップのため、G&Pのプラ製トリガーガードを取り付けていきます。

形状はナイツのやつですね。
G&Pのトリガーガードの穴の内径がプッシュピンとスプリングよりも狭かったので4mmドリルで拡張!!

海外パーツに海外パーツを取り付けるには兎にも角にも加工が必須ですね。
取付完了!

マガジンキャッチはこれを使います。
SP製のアルミ削り出しのやつですね。

アンビでボタンが大型化されています。非常に軽量で18gしかありません。

ボルトリリースレバーは東京マルイ純正のものを使用します。


ロワレシーバーはこんな感じです。
お次はアッパーレシーバーです。
ダミーボルトを取り付けていきます。

このレシーバーに付属していたダミーボルトが取り付けできないってどういうこと~!!!

つくづく微妙ですね~G&Gのマグネシウムレシーバー。
まぁ古い製品なのでしょうがないですね。
怒りを込めてレシーバー側の干渉する段差をリューターで削りました(笑)ダミーボルトの羽をカットするのでも良かったのですがね。

イジェクションポートも付属の物を取り付けましたがロックピンが無いので空きっぱなしという仕様!!う~ん。そのうちマルイのに変えよう。

レシーバーに付属していたボルトフォアードアシストノブが重く感じたので今回はレトロアームズのものを取り付けます。

これもメカボックスと同じようにA7075(超々ジュラルミン)からの削り出しです。
G.A.Wさんで取り扱いがなかったのでレトロアームズの公式通販ページから個人輸入しました。
グレーとブラックを1個づつ注文しましたがほぼ同じ色でした(汗)
左がグレー、右がブラック

肉眼だとよーく目を凝らしてみないと違いが分からないレベルです。
レシーバーに付属していたスチール製のフォアードアシストノブは22g

レトロアームズのノブは8g

微々たる差ですが手に持ってみると結構違いを感じるんですよね。
軽い銃を作るにはこういったパーツ一つ一つの重量が積もりに積もっていくので拘ります。
チャージングハンドルはG&Pのプラスチック製のものにします。軽量です。

めちゃくちゃ大げさなシボ加工がされているうえ、やたらテカテカなのが気になる(笑)
これでアッパーは完成!

アウターはこれを使います。

こんな感じにしました。アウターバレルよりKM企画のサイレンサーの方が軽いのでサイレンサーをアウターの代わりに使う感じですね。

いつものスタイルです(笑)

本当はSLRのハイダーにしてハンドガードとお揃いにしたかったのですが重量が90gもあり、ハイダーの中でも重い方なので今回はナシ。
レールを取り付けるとマズルはほぼツライチになります。

ちょっと寸詰まり感がありますがこんなもんかな~と。
フリップアップサイトとハンドストップでも付ければ印象良くなるんじゃないかなと。
本当はこんなスタイルが理想でした。

諸々組み付けてここまで形になりました。

アウターがこの長さだとインナーバレルは21cmになりますね。今回もこの21cmの長さを基準にメカボックスの中身を作っていくことにします。
セレクターはマガジンキャッチに付いてきたものをとりあえずで付けてみましたがミリタリー感の無い形状をしているのでマルイ純正にしようかな・・・。

トリガーもレトロアームズの面白い形のやつにしましたがまだアルマイト加工(色付け)していないので変更の余地ありですね。
あとはワイヤーストックの軽量化もする予定です。

このロッドがスチール製で重たいので軽量なアルミパイプに置換したいと考えておりますがそれはまた今度ですね。
ということでまた次回!
その④へ
2019年06月18日
超軽量なM4をフルメタルで自作する! その②
その①からの続きです。
その①でも解説しましたが電動ガンはシリンダー、チャンバー、バレルが同一軸線上に位置していなければなりません。
「いや、普通そうなるじゃん」
ごもっともなツッコミでございます。
ただしそれはマトモなメーカーの箱出し電動ガンの場合のみです。
今回のようにバラバラのメーカーのパーツを組み合わせると一見すると分かり辛い微妙な寸法違いが積もり積もって大きなズレとなり、弾道や初速に大きく悪影響を及ぼしてしまう恐れがあります。
マルイの電動ガンのチャンバーを社外製に変えたら初速が下がった!給弾不良を起こすようになった!このパーツダメです使えません!という話をよく聞きます。それはマルイのベストなパーツの位置関係を社外製を入れて崩したから起こることなのです。
社外製のパーツを入れる際は上下左右を調整して真出しし、ノズルも適正な長さの物に変えてBB弾の保持位置を調整するという基本的に守るべきルールさえクリアすればいいのです。相当歪んだチャンバーじゃない限りは大体のメーカーのものは普通に使えますよ。
で!
その①では各パーツの設計のズレなどを仮組みして確認したところ、G&GのマグネシウムレシーバーにレトロアームズのCNCメカボックスを入れるとメカボックスが傾いて固定されることが判明!
今回はそのズレを修正して、シリンダー、チャンバー、バレルを一直線にするところまでいきたいと思います。

↑の写真の穴を見て下さい。
レシーバーのピン穴とメカボックスのピン穴が微妙にズレていることがわかるでしょうか。
これが正しいメカボックスの位置(角度)なのですが、レシーバーの穴がズレている為にこのままピンを挿してしまうとメカボックスが下方に傾いてしまいます。
傾いていても普通に組めたりしますが、ノズルの前後運動に負荷がかかって壊れてしまうことが容易に予想できるので今回はレシーバー側の穴の位置をずらしたいと思います。
今回の施術はまず下記のような流れになります。
レシーバーの穴を上にずらしたいので・・・

上側をリューターで削って楕円の穴を作ります。
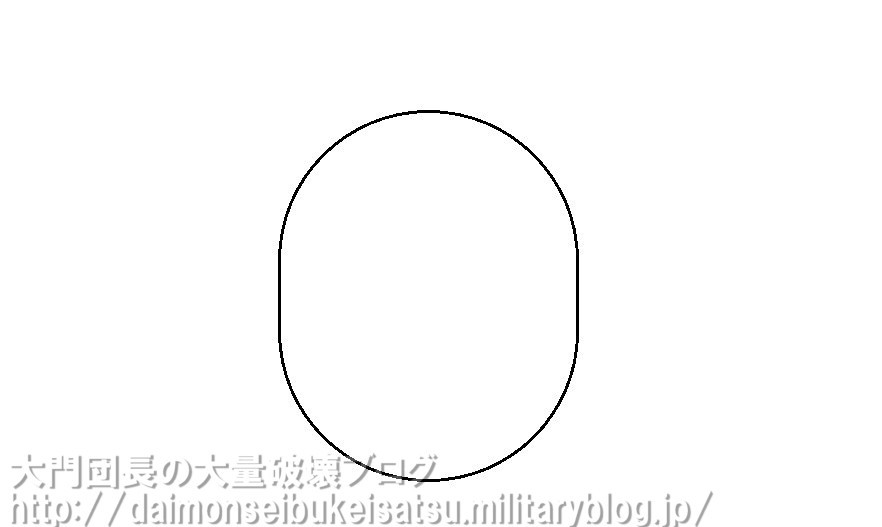
下側をこのように埋めて完成となります。

プラモデル製作やロボットメカの原型製作でもダボ穴の位置を微調整したい場合に行っている手段です。
穴を加工前にここに0.8mm厚のプラ板を貼ってメカボックスが傾かないように下支えします。

まずはリューターでレシーバー側の穴を少し上側に広げました。

今回は穴埋めには瞬間接着剤のシアノンDWを使います。瞬着硬化剤も必要です。

今回のように0.5mm程度の小さな隙間を埋める場合、ポリエステルパテやエポキシパテだと粘度が高すぎて精度の高い仕上がりにならないのと、硬化後もそこまで硬くはならないので使用しません。
シアノンDWは接着用途以外にも隙間のパテ埋めに適しており、硬化後の強度も高いです。
イジェクションポート用の棒が同径だったのでこれを穴埋めの治具として使います。

シリコーンバリアーを塗布してシアノンDWが棒にくっつかないように下処理をしました。
くちびるに塗るメンソレータムでも大丈夫です。
棒をこのように挿して・・・

シアノンDWを隙間に流し込み、スプレープライマーを吹き付けて強制的に硬化させます。

隙間に軽く塗布すれば毛細管現象で勝手に奥まで流れ込んでくれます。
硬化後に棒を抜き取りました。シリコーンバリアーのおかげで棒にはシアノンが付きません。

はみ出た部分をデザインナイフで除去して埋め作業は完了。

最終的にフレームを塗装するのであれば穴の周辺はヤスリでもっと綺麗にして塗装すれば完璧になりますが今のところ、塗装する予定はないのでヤスリは使いませんでした。
アンチローテンションピンだとこのように加工した部分は隠れてしまうので全然問題ナシ!!

ピン位置の調整は完了!
さて、チャンバーとアウターバレルベースを取り付けてみて位置があっているかを確認していきます。
チャンバーはライラクスのワイドユースメタルチャンバーです。

メタルチャンバーは重たいのでもしかしたら今後プラチャンバーにするかもです。
今回は軽さを重視してライラクスのアウターバレルベースを使ってみます。これもメカボックスと同じA7075からの削り出しなので非常に軽量です。

これにアウターバレルピースというエクステンションバレルを継ぎ足していく感じですね。
取り付けようと思ったらこの面が微妙に歪んでてバレルベースがしっかり密着しないことが判明!微妙な湾曲のせいでバレルベースが斜めになってしまいます。
これを無視して取り付けるとバレル自体が傾いてしまいます。例えば20センチくらいのインナーバレルなら先端は中心から3mmくらいズレます。つまり真っすぐ撃ったつもりでもあさっての方向に飛んでいくということになりますので修正は必須ですね。

G&Gのマグネシウムレシーバーはダメダメですね(笑)
鉄ヤスリで面出ししました。

それにしてもこのレシーバー、マグネシウムだから柔らかくて削りやすいですね。プラのレシーバー削ってる時と大差ないです。
サバゲーで使用している時の強度がかなり心配・・・!
お!ビタっと密着してガタは無くなりました!

アウターバレルベースをしっかりと固定し、各パーツが同軸線上に配置されているかを確認していくのでハンドガードに付属しているバレルナットも取り付けていきます。

ハンドガードはDYTACのSLR 6.7" Helix Ultra Lite M-LOK Railを選定しました。SLR社の正式ライセンス商品です。
カッコいいしとにかく軽い!
因みに6.7インチのHelixのM-LOKバージョンは日本には入ってきていないので香港のショップから個人輸入しました。
KeyModバージョンは日本に入ってきていましたが即完売していましたね。
ということで仮組み!

うむ、真出しは大丈夫かと!
シリンダー位置、チャンバー、アウターバレルの中心線が同じになりました。
主要部品の仮組みした姿がこちら!なかなかイイ感じじゃないか!?

主要部品は全て別のメーカーです。

やはりここまでバラバラだとパーツの合いをいちいちチェックして修正していかないといけないので大変ですね。
VFCとかライラクスだけとかならそこまで苦労しない気もしますが。
ミリタリー感を出す為にA2グリップでもいいかな~と思ったり。

現時点での重さはなんとたったの783g!!フルメタルでこれですよ!

これだけ組んで783gならメカボックス組んでモーターとかバレル入れてもかなり軽く仕上がる予感!!
もしかしたらフルメタルで1500g以下に収められるかも!?
ということでまた次回!
その③へ
その①でも解説しましたが電動ガンはシリンダー、チャンバー、バレルが同一軸線上に位置していなければなりません。
「いや、普通そうなるじゃん」
ごもっともなツッコミでございます。
ただしそれはマトモなメーカーの箱出し電動ガンの場合のみです。
今回のようにバラバラのメーカーのパーツを組み合わせると一見すると分かり辛い微妙な寸法違いが積もり積もって大きなズレとなり、弾道や初速に大きく悪影響を及ぼしてしまう恐れがあります。
マルイの電動ガンのチャンバーを社外製に変えたら初速が下がった!給弾不良を起こすようになった!このパーツダメです使えません!という話をよく聞きます。それはマルイのベストなパーツの位置関係を社外製を入れて崩したから起こることなのです。
社外製のパーツを入れる際は上下左右を調整して真出しし、ノズルも適正な長さの物に変えてBB弾の保持位置を調整するという基本的に守るべきルールさえクリアすればいいのです。相当歪んだチャンバーじゃない限りは大体のメーカーのものは普通に使えますよ。
で!
その①では各パーツの設計のズレなどを仮組みして確認したところ、G&GのマグネシウムレシーバーにレトロアームズのCNCメカボックスを入れるとメカボックスが傾いて固定されることが判明!
今回はそのズレを修正して、シリンダー、チャンバー、バレルを一直線にするところまでいきたいと思います。

↑の写真の穴を見て下さい。
レシーバーのピン穴とメカボックスのピン穴が微妙にズレていることがわかるでしょうか。
これが正しいメカボックスの位置(角度)なのですが、レシーバーの穴がズレている為にこのままピンを挿してしまうとメカボックスが下方に傾いてしまいます。
傾いていても普通に組めたりしますが、ノズルの前後運動に負荷がかかって壊れてしまうことが容易に予想できるので今回はレシーバー側の穴の位置をずらしたいと思います。
今回の施術はまず下記のような流れになります。
レシーバーの穴を上にずらしたいので・・・

上側をリューターで削って楕円の穴を作ります。
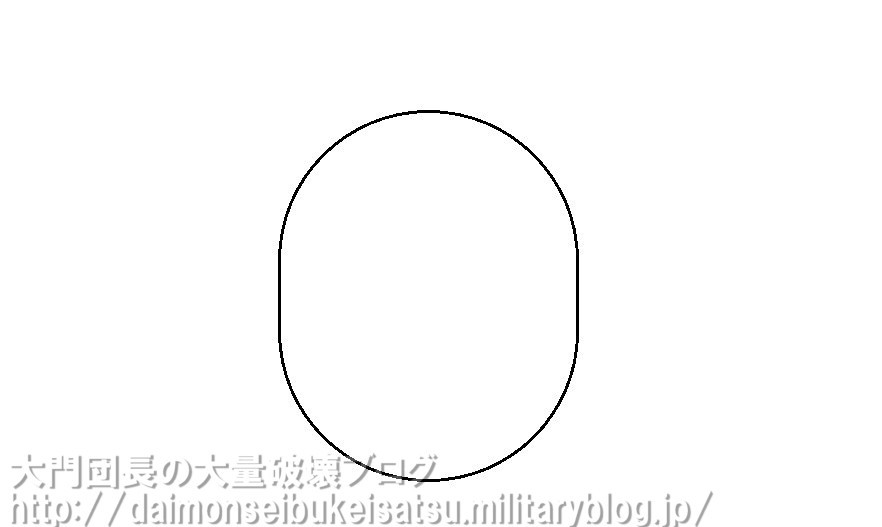
下側をこのように埋めて完成となります。

プラモデル製作やロボットメカの原型製作でもダボ穴の位置を微調整したい場合に行っている手段です。
穴を加工前にここに0.8mm厚のプラ板を貼ってメカボックスが傾かないように下支えします。

まずはリューターでレシーバー側の穴を少し上側に広げました。

今回は穴埋めには瞬間接着剤のシアノンDWを使います。瞬着硬化剤も必要です。

今回のように0.5mm程度の小さな隙間を埋める場合、ポリエステルパテやエポキシパテだと粘度が高すぎて精度の高い仕上がりにならないのと、硬化後もそこまで硬くはならないので使用しません。
シアノンDWは接着用途以外にも隙間のパテ埋めに適しており、硬化後の強度も高いです。
イジェクションポート用の棒が同径だったのでこれを穴埋めの治具として使います。

シリコーンバリアーを塗布してシアノンDWが棒にくっつかないように下処理をしました。
くちびるに塗るメンソレータムでも大丈夫です。
棒をこのように挿して・・・

シアノンDWを隙間に流し込み、スプレープライマーを吹き付けて強制的に硬化させます。

隙間に軽く塗布すれば毛細管現象で勝手に奥まで流れ込んでくれます。
硬化後に棒を抜き取りました。シリコーンバリアーのおかげで棒にはシアノンが付きません。

はみ出た部分をデザインナイフで除去して埋め作業は完了。

最終的にフレームを塗装するのであれば穴の周辺はヤスリでもっと綺麗にして塗装すれば完璧になりますが今のところ、塗装する予定はないのでヤスリは使いませんでした。
アンチローテンションピンだとこのように加工した部分は隠れてしまうので全然問題ナシ!!

ピン位置の調整は完了!
さて、チャンバーとアウターバレルベースを取り付けてみて位置があっているかを確認していきます。
チャンバーはライラクスのワイドユースメタルチャンバーです。

メタルチャンバーは重たいのでもしかしたら今後プラチャンバーにするかもです。
今回は軽さを重視してライラクスのアウターバレルベースを使ってみます。これもメカボックスと同じA7075からの削り出しなので非常に軽量です。


これにアウターバレルピースというエクステンションバレルを継ぎ足していく感じですね。
取り付けようと思ったらこの面が微妙に歪んでてバレルベースがしっかり密着しないことが判明!微妙な湾曲のせいでバレルベースが斜めになってしまいます。
これを無視して取り付けるとバレル自体が傾いてしまいます。例えば20センチくらいのインナーバレルなら先端は中心から3mmくらいズレます。つまり真っすぐ撃ったつもりでもあさっての方向に飛んでいくということになりますので修正は必須ですね。

G&Gのマグネシウムレシーバーはダメダメですね(笑)
鉄ヤスリで面出ししました。

それにしてもこのレシーバー、マグネシウムだから柔らかくて削りやすいですね。プラのレシーバー削ってる時と大差ないです。
サバゲーで使用している時の強度がかなり心配・・・!
お!ビタっと密着してガタは無くなりました!

アウターバレルベースをしっかりと固定し、各パーツが同軸線上に配置されているかを確認していくのでハンドガードに付属しているバレルナットも取り付けていきます。

ハンドガードはDYTACのSLR 6.7" Helix Ultra Lite M-LOK Railを選定しました。SLR社の正式ライセンス商品です。
カッコいいしとにかく軽い!
因みに6.7インチのHelixのM-LOKバージョンは日本には入ってきていないので香港のショップから個人輸入しました。
KeyModバージョンは日本に入ってきていましたが即完売していましたね。
ということで仮組み!

うむ、真出しは大丈夫かと!
シリンダー位置、チャンバー、アウターバレルの中心線が同じになりました。
主要部品の仮組みした姿がこちら!なかなかイイ感じじゃないか!?

主要部品は全て別のメーカーです。

やはりここまでバラバラだとパーツの合いをいちいちチェックして修正していかないといけないので大変ですね。
VFCとかライラクスだけとかならそこまで苦労しない気もしますが。
ミリタリー感を出す為にA2グリップでもいいかな~と思ったり。

現時点での重さはなんとたったの783g!!フルメタルでこれですよ!

これだけ組んで783gならメカボックス組んでモーターとかバレル入れてもかなり軽く仕上がる予感!!
もしかしたらフルメタルで1500g以下に収められるかも!?
ということでまた次回!
その③へ
2019年06月13日
東京マルイ ガスブローバック FNX-45 レビュー!
結構心待ちにしていたFNX-45をレビューしてみたいと思います。
かなりタクティカル感の強いデザインで好きです。

まずは実銃の解説になります。
2005年に米軍がJoint Combat Pistolという正式サイドアームの更新を計画しました。
その際にメーカー各社に出した条件が45ACP弾を使うこと、大容量マガジン、ピカティニレールを搭載していること、バレルにサプレッサーを付けられること、フレームがダークアースカラーであることが条件でした。
その際にFNハースタル社のアメリカ支社が提示したのがFNP-45でした。
しかし、いろいろあってJoint Combat Pistol自体が無期延期になってしまい、そこでFN社がFNP-45を改良して市場向けに発売したのがFNX-45 Tacticalというわけです。
因みにJoint Combat Pistolにはお馴染みのHK45やPx4も参加していました。
ガスブロでは5年前くらいにフランスのCybergunというメーカーからFN社正式ライセンスのFNX-45が発売されました。
日本国内では30000円前後の価格で販売されています。
それがトイガンで唯一のFNX-45でしたがこの度、マルイからようやく発売という流れですね。
マルイのFNX-45は定価が17800円、実勢価格が14500円前後。ありがとうマルイ。
ということでレビューしていきたいと思います。
HK45と同じ箱の大きさでした。45口径弾のオートマチックピストルはこの箱なのかな?

相変わらず高級感のある箱に収められています。
レビューには毎回書きますがこういう化粧箱は大事なのですよ。
ユーザーに対して上等なオモチャを買ったのだという充足感を与えるのに一役買っています。
さて、取り出してみた。

広告などで見てた時はグリップなんかは細身な印象だったのですが、実際に持ってみると太い!デカイ!がファーストインプレッション。
やはり45口径ということで存在感は抜群!
写真だとバレルとグリップの比率の問題でそんなに大きく見えないのかもしれません。
ハイキャパとグロック19と比較するとこのくらいの大きさ。

スライドもFNX-45のが分厚いですね。

グリップはかなり強めのチェッカリングが施されています。素手でギュッっと握るとなかなか来ます(笑)

表面はメタルスライド感を出す為に塗装が施されています。

スライドリリースレバー、マガジンリリースボタン、セーフティレバー、全てがアンビ(左右対称)になっています。

完全にアンビになっているというのは左利きの人には良いかもしれませんね。
もちろんスライドリリースレバーのツメが掛かる部分にはスライドの内側に亜鉛合金の補強が入っているのでスライドの切り欠きが削れる心配はありません。
上から見るとこんな感じ。
実際はハイキャパと同じくらいの長さです。
実銃同様にドットサイトが付けられるようになっています。

実銃にはRMRなどの小型ドットサイトが取り付けられますがこのFNX-45にはマルイのマイクロプロサイトが取付可能となっています。
サイレンサーを付けた時にも照準ができるようにハイサイトが最初から搭載されています。


ハイサイトってタクティカル感あっていいですよね~!!
ただ、リアサイトの横にゲート跡が残っているのがちょっとアレかな~パーティングラインは大目に見てもゲート跡は見えないところにして欲しかったかも・・・。
サイトビュー

マガジンは29発入ります。
実銃は45ACPが15発も入るようです。
ホールドオープン。

なかなかカッコイイぞ!
ちょっと弄ってて気になったのがデコッキングがやりにくいことですね。

普通に押し下げただけでは何も起こらず、レバーを弾くように下げて離すとデコックされます。
う~んここはちょっと微妙。
最近のポリマーフレームオートでは当たり前のバックストラップがもちろんFNX-45にもついています。しかも今回は4パターンも!

チェッカリングタイプのM・LとリブタイプのM・Lが付属しています。
因みに最初に付いているのはチャッカリングのLです。
LとMの差はこんな感じ。結構違いますね。

バックストラップは硬質ゴムで出来ていて、下からスライドして取り付けます。

横縞模様のリブタイプよりもチェッカリングの方が尖っている分太さがあるので今回はリブタイプのMにしてみました。

グリップの印象が変わりましたね。細くなって握り易くなりました。

グリップとバックストラップとの隙間がちょっと気になるかな??
せっかくなのでマイクロプロサイトを装着してみました。カッコイイ!

カッコいいけどマイクロプロサイトはデザインがシンプル過ぎるのでRMRの方が似合いそうではある。

結構深い位置までマイクロプロサイトが食い込んでいますね。
因みにトリジコンのRMRはこんなやつ

フル装備!タクティカル臭がプンプンでたまらないですね!

サイレンサーはガスブロのHK45に付属していたやつです。
ガスブロ HK45のレビューはコチラ
FNX-45用にFDEカラーの同型サイレンサーも発売されましたが流石に色違いで2つも要らんなと思って買いませんでした(笑)
ライトはド定番のX300Uです。
SOCOM MK23のサイレンサーも付きます。

さて、スライドを外して軽く中身を見ていきたいと思います。

いちいちスライドを外さないとホップを調整できないタイプです。

ガスルートが従来のモデルよりも大口径になっていますね。

ブリーチを外してみました。

ガバメント系と同じでスライドをグイっと広げてやるとブリーチが取れますがスライドが分厚くて広げるのが結構大変。
かなり気合を入れないと取れません。
よほどの用事がない限りは取らないようにしましょう。
シリンダーが薄い!!!

説明書によるとドットを載せられるようにするにはかなり制約が多く、このようにシリンダーをつぶした形にすることで決着がついたようです。

ということで初速をチェック!マガジンにはガスを半分入れて25度に温めた状態です。

弾はマルイの0.2gのプラ弾でホップちょいかけ状態で、1秒おきに8発撃った時の変化です。
このサイズのガスブロにしては若干低いかな?という印象。
でもまぁこんなものでしょう。
で、ブローバックですが、躯体に似合わずかなりのスピード!!
マガジンのガスと温度を同じ条件にしたハイキャパよりもブローバックは俊敏で衝撃も強めです。
この質量でこのブローバックのスピードはなかなかではないでしょうか。
マルイのガスブロの中でもブローバックの迫力はかなり上の方だと思います。
衝撃が手首にまでくる感じです。
ということで総評です。
今まではCybergunの高いやつを買わないといけなかったところ、マルイさんから手の伸ばしやすい価格で発売されたというところでまずは歓喜すべきところでしょう。
デコックができなかったりするところが微妙でしたがそれ以外はなかなか良かったかと思います。

あと、スライドの色は塗装ですから剥げてしまわないように注意ですね。


剥げたら↑のようなプラ地が出てきてしまいますので。
それ以外は特段気になるところはなく、非常に良い機種だと感じました。
まずこの銃の生い立ちがタクティカルだし各部の機能もミリタリーユースを意識して作られているのでミリオタ的要素のある人にはかなりウケが良いかと思います。
レールはもちろん、ドットやサイレンサーが簡単に付けられるのも良いですね。
装弾数も29発ということでガスブロの中では多いほうですし、ドットを付ければかなり戦いやすいのでサバゲーでガスブロをガンガン使いたいという方に向いている機種かと思います。
ダークアースカラーもいいけどブラックも欲しいな~!
過去のマルイさんのパターンを見る限りではFNX-45のカラーバリエーションは2年以内に100%出すと思いますのでそれを待ちたいと思います。
かなりタクティカル感の強いデザインで好きです。

まずは実銃の解説になります。
2005年に米軍がJoint Combat Pistolという正式サイドアームの更新を計画しました。
その際にメーカー各社に出した条件が45ACP弾を使うこと、大容量マガジン、ピカティニレールを搭載していること、バレルにサプレッサーを付けられること、フレームがダークアースカラーであることが条件でした。
その際にFNハースタル社のアメリカ支社が提示したのがFNP-45でした。
しかし、いろいろあってJoint Combat Pistol自体が無期延期になってしまい、そこでFN社がFNP-45を改良して市場向けに発売したのがFNX-45 Tacticalというわけです。
因みにJoint Combat Pistolにはお馴染みのHK45やPx4も参加していました。
ガスブロでは5年前くらいにフランスのCybergunというメーカーからFN社正式ライセンスのFNX-45が発売されました。
日本国内では30000円前後の価格で販売されています。
それがトイガンで唯一のFNX-45でしたがこの度、マルイからようやく発売という流れですね。
マルイのFNX-45は定価が17800円、実勢価格が14500円前後。ありがとうマルイ。
ということでレビューしていきたいと思います。
HK45と同じ箱の大きさでした。45口径弾のオートマチックピストルはこの箱なのかな?

相変わらず高級感のある箱に収められています。
レビューには毎回書きますがこういう化粧箱は大事なのですよ。
ユーザーに対して上等なオモチャを買ったのだという充足感を与えるのに一役買っています。
さて、取り出してみた。

広告などで見てた時はグリップなんかは細身な印象だったのですが、実際に持ってみると太い!デカイ!がファーストインプレッション。
やはり45口径ということで存在感は抜群!
写真だとバレルとグリップの比率の問題でそんなに大きく見えないのかもしれません。
ハイキャパとグロック19と比較するとこのくらいの大きさ。

スライドもFNX-45のが分厚いですね。

グリップはかなり強めのチェッカリングが施されています。素手でギュッっと握るとなかなか来ます(笑)

表面はメタルスライド感を出す為に塗装が施されています。

スライドリリースレバー、マガジンリリースボタン、セーフティレバー、全てがアンビ(左右対称)になっています。

完全にアンビになっているというのは左利きの人には良いかもしれませんね。
もちろんスライドリリースレバーのツメが掛かる部分にはスライドの内側に亜鉛合金の補強が入っているのでスライドの切り欠きが削れる心配はありません。
上から見るとこんな感じ。

実際はハイキャパと同じくらいの長さです。
実銃同様にドットサイトが付けられるようになっています。

実銃にはRMRなどの小型ドットサイトが取り付けられますがこのFNX-45にはマルイのマイクロプロサイトが取付可能となっています。
サイレンサーを付けた時にも照準ができるようにハイサイトが最初から搭載されています。


ハイサイトってタクティカル感あっていいですよね~!!
ただ、リアサイトの横にゲート跡が残っているのがちょっとアレかな~パーティングラインは大目に見てもゲート跡は見えないところにして欲しかったかも・・・。
サイトビュー

マガジンは29発入ります。

実銃は45ACPが15発も入るようです。
ホールドオープン。

なかなかカッコイイぞ!
ちょっと弄ってて気になったのがデコッキングがやりにくいことですね。

普通に押し下げただけでは何も起こらず、レバーを弾くように下げて離すとデコックされます。
う~んここはちょっと微妙。
最近のポリマーフレームオートでは当たり前のバックストラップがもちろんFNX-45にもついています。しかも今回は4パターンも!

チェッカリングタイプのM・LとリブタイプのM・Lが付属しています。
因みに最初に付いているのはチャッカリングのLです。
LとMの差はこんな感じ。結構違いますね。

バックストラップは硬質ゴムで出来ていて、下からスライドして取り付けます。

横縞模様のリブタイプよりもチェッカリングの方が尖っている分太さがあるので今回はリブタイプのMにしてみました。

グリップの印象が変わりましたね。細くなって握り易くなりました。

グリップとバックストラップとの隙間がちょっと気になるかな??
せっかくなのでマイクロプロサイトを装着してみました。カッコイイ!

カッコいいけどマイクロプロサイトはデザインがシンプル過ぎるのでRMRの方が似合いそうではある。

結構深い位置までマイクロプロサイトが食い込んでいますね。
因みにトリジコンのRMRはこんなやつ
フル装備!タクティカル臭がプンプンでたまらないですね!

サイレンサーはガスブロのHK45に付属していたやつです。
ガスブロ HK45のレビューはコチラ
FNX-45用にFDEカラーの同型サイレンサーも発売されましたが流石に色違いで2つも要らんなと思って買いませんでした(笑)
ライトはド定番のX300Uです。
SOCOM MK23のサイレンサーも付きます。

さて、スライドを外して軽く中身を見ていきたいと思います。

いちいちスライドを外さないとホップを調整できないタイプです。

ガスルートが従来のモデルよりも大口径になっていますね。

ブリーチを外してみました。

ガバメント系と同じでスライドをグイっと広げてやるとブリーチが取れますがスライドが分厚くて広げるのが結構大変。
かなり気合を入れないと取れません。
よほどの用事がない限りは取らないようにしましょう。
シリンダーが薄い!!!

説明書によるとドットを載せられるようにするにはかなり制約が多く、このようにシリンダーをつぶした形にすることで決着がついたようです。

ということで初速をチェック!マガジンにはガスを半分入れて25度に温めた状態です。

弾はマルイの0.2gのプラ弾でホップちょいかけ状態で、1秒おきに8発撃った時の変化です。
このサイズのガスブロにしては若干低いかな?という印象。
でもまぁこんなものでしょう。
で、ブローバックですが、躯体に似合わずかなりのスピード!!
マガジンのガスと温度を同じ条件にしたハイキャパよりもブローバックは俊敏で衝撃も強めです。
この質量でこのブローバックのスピードはなかなかではないでしょうか。
FNX-45のレビュー記事は書き終えたけど遅い時間になったのでブログの更新は明日の夜になります。
— 大門団長@STINGERオーナー (@daimondanchou) 2019年6月12日
大柄なのにも関わらずブローバックがかなり強め&鋭いので今までの機種の中ではかなり迫力がある方だと思います。
レベサバでのレビュー動画のアップももう少し先になります。 pic.twitter.com/OJyy0umDkd
マルイのガスブロの中でもブローバックの迫力はかなり上の方だと思います。
衝撃が手首にまでくる感じです。
ということで総評です。
今まではCybergunの高いやつを買わないといけなかったところ、マルイさんから手の伸ばしやすい価格で発売されたというところでまずは歓喜すべきところでしょう。
デコックができなかったりするところが微妙でしたがそれ以外はなかなか良かったかと思います。

あと、スライドの色は塗装ですから剥げてしまわないように注意ですね。


剥げたら↑のようなプラ地が出てきてしまいますので。
それ以外は特段気になるところはなく、非常に良い機種だと感じました。
まずこの銃の生い立ちがタクティカルだし各部の機能もミリタリーユースを意識して作られているのでミリオタ的要素のある人にはかなりウケが良いかと思います。
レールはもちろん、ドットやサイレンサーが簡単に付けられるのも良いですね。
装弾数も29発ということでガスブロの中では多いほうですし、ドットを付ければかなり戦いやすいのでサバゲーでガスブロをガンガン使いたいという方に向いている機種かと思います。
ダークアースカラーもいいけどブラックも欲しいな~!
過去のマルイさんのパターンを見る限りではFNX-45のカラーバリエーションは2年以内に100%出すと思いますのでそれを待ちたいと思います。



